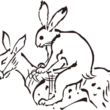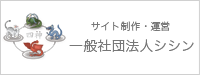広告
adsense4

今から数年前世界中を震撼させた新型感染症、コロナウイルスの脅威の記憶はいまだ我々の心に新しいところだと思います。
人々の生命を脅かしたウイルスの恐怖もさることながら、感染症は我々の日々の暮らしや経済活動に深刻な打撃を与えました。
とりわけ飲食店が被った被害は絶大で、コロナ禍で倒産に追い込まれた飲食店の総数は、日本全体で15000軒に上ったとの帝国データバンクの報告があるほどです。
ところが一方で、そんな時代の逆風をものともせずに悠々と営業を続けていた飲食業があるのです。
それは、他ならぬ京都のパン屋です。
かねてよりパン屋の数が多いことで知られる京都でしたが、コロナ禍で店を閉めたところはほとんどないといわれます。
それどころか、中にはわざわざコロナの時期に新しく開店した店もあるほどです。
いったいどこにその理由があるのでしょうか?

職住一体の街、京都の特質
それは、京都独特の街の造りにあります。
京都の街はいわゆる職住一体と呼ばれます。
職住一体とは別名、職住近接とも呼ばれ、簡単に言えば仕事場と住居を一体化させる、または近接化させることを指します。
具体的には自宅にオフィスを設けたり、工房を設ける、店舗付き住宅に住むなどがその例として挙げられます。

四条烏丸の街並み
上記の写真は四条烏丸付近の街並みですが、見てお分かりの通り京都の街はオフィスが立ち並ぶ繫華街であっても、そこに住宅が混在しています。
これもまた職住一体のもう一つの側面と言って差し支えないでしょう。
つまり、東京や大阪などの都市の場合、働いている人がそのままそこに住んでいる、ということはまず考えられいでしょう。
ほとんどのサラリーマンは郊外に住居を持ち、遠方から通勤してくるのが普通です。
ところがそれに対して京都では、オフィス街の中でも住宅が厳然と存在している。
これがコロナ禍でも京都のパン屋が一人、気を吐いていた最大の理由です。
東京や大阪などの都市では、コロナによって多くの企業がリモートワークを導入しました。
それはすなわち、都市のオフィス街から人気がなくなることを意味します。
するとその影響をもろに受けて、都会のパン屋では客足が途絶えてしまいます。
たちまち売り上げが落ちるわけです。
その結果、廃業に追い込まれる。
これに反し、京都のパン屋はオフィス街にも住宅がしっかりあることから在宅ワークが増えても売り上げに響くことはありません。
事実、オフィス街である四条通や三条通でもコロナの時期に新規オープンしたパン屋は何軒もあります。

先に、職住一体の具体的な例として自宅に工房を設けると挙げましたが、西陣織や京友禅などの着物産業をはじめ、京漆器や京焼、清水焼などの工芸品などはご存じの通り、自宅が職人さんたちの工房となっています。
こうした職人たちの間では、昔からパンは非常に重宝されてきました。
例えば西陣織や京友禅などのいとへん産業が盛んだった昭和30~40年代、職人たちは夜なべに次ぐ夜なべの毎日でした。
そんな夜間の仕事の合間ちょっと小腹がすいたとき、職人たちは好んでパンを口にしました。

西陣織の職人が仕事をしている
麵類などを食べたらうっかりミスで汁を反物に落としかねない、ご飯は粘っこいご飯粒が反物の生地にくっつくことがある。
その点、そうした心配のないパンは、仕事の合間、職人たちが手を休めずに気軽に口に運べる軽食だったのです。
京都の主要な伝統産業に携わる職人たちから支持を受けてきたことが、逆風下でも古都京都でパンが強い秘密の一つと言えるでしょう。
スライス食パン誕生と古都の秘密
さて、従来より京都の職人たちに愛されてきたパンですが、長い間それは菓子パンに限られていました。
職人たちに喜ばれたのはアンパンやジャムパンなどの甘い菓子パンだったのです。

戦後復興期、いとへん産業の景気の上昇とともに菓子パンの売り上げは右肩上がりでしたが、その一方でさっぱり人気のなかったのが食パンでした。
敬遠されていたといった方がよいかもしれません。
それを憂えていたのが現在でも老舗ベーカリーとして知られる進々堂の2代目社長の続木真那という人でした。
何とかして食パンを主力製品にしたいと考えあぐねていた矢先、続木社長は手にしたアメリカのパンの雑誌にふと目を止めます。
その雑誌にはスライスした食パンが家庭の食卓においてある写真が掲載されていました。
「ほう、アメリカでは食パンをスライスして販売しているのか?」ということに社長は感心しました。
戦後10年が経過した当時、日本の食パンはまだ切らずに販売されていたのです。
日本でもスライスして売れば、食パンはもっと食べてもらえるかもしれない。
こう考えた続木社長は、直ちに食パンをスライスする機械と自動で包装機械を輸入したのです。
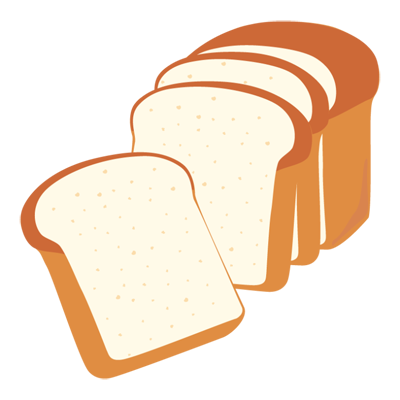
こうして1953年(昭和28年)、日本で初めてスライス食パン「デイリーブレッド」が進々堂から発売されました。
それを契機に京都の食パンの売り上げは爆発的に伸びることとなり、やがて食パンはスライスして売るものという概念は日本全国に浸透していったのです。
むすび
以上、簡単に見てきたように今も昔も古都京都ではパンが愛され喜ばれていますが、それには独特の理由があるのです。
コロナ禍という世界的に大変な状況をもものともしなかった京都のパン屋の底力もさることながら、スライス食パンの発想をはじめとする(ここでは触れませんでしたが)フランスパンの製造などの日本初の取り組みにおいても、京都にまつわるパンの秘密は大変奥が深いのです。
この記事を書いた人
つばくろ(Tsubakuro)
京都生まれ、京都育ち、生粋の京都人です。
若い頃は京都よりも賑やかな東京や大阪に憧れを抱いていましたが、年を重ねるに従って少しづつ京都の良さが分かってきました。
このサイトでは、一見さんでは見落してしまう京都の食を巡る穴場スポットを紹介します。