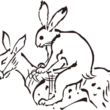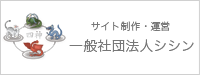無粋なお人は棺桶に入るまで気がつかあらへんかもしれへんなぁ、 いけずな京ことば“お断り篇”
投稿日:2025年07月03日投稿者:つばくろ(Tsubakuro)
カテゴリー:京ことば , 京都よもやま話
広告
adsense4


無粋なお人は棺桶に入るまで気がつかあらへんかもしれへんなぁ、いけずな京ことば“お断り篇”
本音と建て前を駆使して会話するのが典型的な京都人。
京ことばの基本はあいまいさの一言に尽きるといっても過言ではないでしょう。
婉曲的でやんわりとしたいいまわしでありながら、相手の心にじんわりとこたえる独特のことば使い。―――これがよそさんからは“いけず”と恐れられているようです。
まぁ、本当に京都人が“いけず”であるか否か、その真偽のほどは別として、京ことばの持つ数々の含みがいかんなく発揮されるのは、お断りの場面ではなかろうかと思います。
これからご紹介する京ことばの様々なお断り表現は、よその土地の人たちではなかなか操れない高等なコミュニケーション戦術だといえるかもしれません。

例―――
①あまり自分とは関係が深くない人から、無理なお願いをされてしまった。
それを断りたいとき。
「いや、うれしおすけどうちにはちょっと。もっと上手にしはる人探しまひょか。」
或いは、
「ちょっと考えさせてもろてかましまへんか。ちょうど今さっき、恩義のあるお人からお願い事をされてしもてなぁ。今、頭がいっぱいで考えられへん。ちょっと時間もろてかましまへんか。すんまへんなぁ。」
京ことばでは、“ちょっと~”と言われたら、まず断られたと解釈して差し支えありませんね。
“ちょっと~”の後にどんなことばが続いても、それは結局お断りであることに変わりはありません。
さらに、下のお断りの例では「恩義のある人から頼まれごとをされた」とまでわざわざ言っており、暗に「おたくは自分にとっては恩義のない人や。」とほのめかしています。
京ことば特有のいけずで効果的な言い回しです。
②それでもなお、執拗に踏み込まれたら?
「いや、かなんなぁ。けったいなお人やわぁ。堪忍しとうくれやす。」
これは、最大級の怒り・拒絶のアピール。
面と向かってけったいなお人と言われたら、京都人から最大に侮蔑されたといってもよいくらいです。
これで察しなかったら、京都ではそれ以降相手にしてもらえなくなります。
③来てもらいたくない人から申し込みの電話が入った。
それを断るとき。
「おおきに。またええ時にお電話させてもらいます。」(と言って、一生かけてこない。)
「すみません。あいにくその日は予定があって。」というと、別な日を申し込まれる恐れがあります。
それに対して、こちらから電話すると言っておくことで、相手の次のアクションを封じてしまうという典型的な京ことばのお断りのサンプルです。
④つまらないアイデアを提示された。
それを却下したいとき。
「それ、おもしろおすなぁ。」
京都で面と向かっていきなり「面白い」と言われたら、それは褒めことばではありません。
それは「妙な」とか「理解できない」とか或いは「頭が悪い。」といった軽蔑の意味を含んでいます。
つまり、「おもしろおすなぁ。」とはっきりいわれることは「おたくのいうことは受け入れられません。理解できません。」と言われたに等しいのです。
⑤理不尽な文句を言ってこられたときは?
「いやぁ。おもしろいこといわはるわぁ。けったいなお人やわぁ。なるほど、そうどすか。そら、えらいすんまへん。私ら不調法ですさかい、ようわかりまへんけど。ええ勉強させてもらいました。おおきに。」
「おもしろいこといわはるわぁ。」といった後で、「私ら不調法ですさかい、ようわかりまへん」と表向きは謙遜しつつ、相手を痛烈に攻撃しています。
おまけに「ええ勉強させてもらいました。おおきに。」で締めくくっているあたり、相手にとどめを刺す一撃ですね。
⑥寄付や慈善活動、入るつもりのない宗教などの勧誘を受けて困っているとき。
「うちにはもったいないお話で。」
或いは
「考えときます。」
或いは
「3代前がそれで家をつぶしかけまして。」
⑦習い事やサークル活動をやめたいとき。
「しばらく休ませてもらいます。」
京都人にこれをいわれたら、絶対「次はいつ再開されますか?などと聞いてはいけません。
⑧早く帰ってほしい相手に長居されて困ったとき。
「さ、長いこと引っ張ってしもてすんまへん。お忙しいのに、おおきに。ほな!」
「さ、」とひと言発することで、相手に腰を上げるきっかけを促して、その場の空気を一変させます。
あくまでも建前は相手にお詫びと感謝を伝えておきながら、こちらの真意をやんわりとニュアンスで伝えています。
これをいわれたら、潔く腰を上げて「長居してすみませんでした。」とわ詫びましょう。
⑨長電話をそろそろ切りたいとき。
「ほな、そういうことで。」
或いは、
「ほな、また。」
或いは、
「ほな、よろしゅうに。」
京ことばで「ほな」といわれたら、「話が長い。」、「話はもう結構。」といわれたのと同じです。
「ほな」は後に続く会話を遮る便利なフレーズです。
⑩しつこい営業マンなどに無理強いされて困ったときの撃退方法は?
「主人に聞いてみんとわかりませんし。」
或いは、
「私はええ思うんどすけど、社長に相談してみんことには。」、
取引先や客などから無茶なお願いをされて困ったとき、京都人が使う王道のお断りパターンです。
面と向かって「断ります。」というのは角が立つ。
そういう際に、何の脈絡もなしにいきなりキーパーソンの名前が出てくるわけです。
うわべはあくまでもへりくだりつつ、きちんとお断りするのです。

むすび
以上、具体的な例を挙げつつ、やんわりとした含みのある京ことばを駆使したお断り表現を紹介してきました。
こうした言い回しは、日常生活の中で折に触れ京都人が用いるものと言って差し支えありません。
これらの表現には、相手を傷つけかねないはっきり「お断りする」という行為のショックを極力和らげるためのいくつかのポイントが挙げられます。
それは、
①相手を立てることばを使っていること。
②遠回しな表現に終始すること。
③曖昧さをはらんだことばを選んでいること。
④決して頭ごなしに否定しないこと。
などです。
こうした点を抑えながら、その時その場の状況に応じて巧みにことばを操っているのが京都人と言えるでしょう。
最後に、実際にコラム子が味わった忘れられない「お断り」の体験談をご紹介しておきます。
小学校時代の親友と何十年ぶりかで再会した時のこと。
互いに再会を喜び合った後、友人が「学校を出てから、その後どうしてたん?」と聞きました。
コラム子は、そのことばを真に受けてこれまでのことを話し始めました。
すると、友人は「ほんまに~なぁ。」と相槌を打ったのです。
なおもこちらが話していると、再び「ほんまに~なぁ。」。
もう少し話したら、すかさず「ほんまに~なぁ。」
さすがに、コラム子もそこで気がついて話すのをやめました。
幼なじみの「その後どうしてたん?」ということばは単なる表向きの社交辞令的な問いかけに過ぎなかったのです。
友人の「ほんまに~なぁ。」に、先にあげた例のような毒はなかったにせよ、1度聞いたら忘れられない京ことばの1つでした。
「ええ加減その話切り上げてんか。」という友人の本音が充分に伝わってくるどんぴしゃりのお断り表現だったと今でもよく思い出します。
この記事を書いた人
つばくろ(Tsubakuro)
京都生まれ、京都育ち、生粋の京都人です。
若い頃は京都よりも賑やかな東京や大阪に憧れを抱いていましたが、年を重ねるに従って少しづつ京都の良さが分かってきました。
このサイトでは、一見さんでは見落してしまう京都の食を巡る穴場スポットを紹介します。