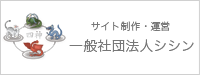広告
adsense4
はじめに
何年か前のことです。
ある知り合いのお宅をお借りして、ちょっとした集いの場が設けられたことがありました。
その席で、会場を提供してくれたお宅の奥さんが、参加者にお茶をふるまわれたのです。
集まっていた人は皆お礼をいって、出されたお茶を飲んでいたのですが、だしぬけにある男の人の声が響き渡りました。
「あ~あ。やっぱりなんていうても番茶が一番どすなあ。気い使わんと飲めまっさかいなあ。」
すると、すかさず会場提供者の奥さんがこういい返したのです。
「おことばを返すようで申し訳あらしまへんけど、これは番茶やおへんのどすわ。ほうじ茶どす。うっとこは番茶は飲ましまへんさかいに。」
冷静でしたが同時ににべもなく相手のことばを切って捨てる口調でした。
二人のやり取りを聞いて、一同は静まり返りました。
よっぽどばつが悪かったのでしょう。
いい出しっぺの男の人はしばらくして「えへへへへ。」と笑ったきりその場から姿を消してしまいました。
その人物がいなくなってから、残った人たちはその人のことを異口同音にけなし始め、座は大いに盛り上がりました。
「番茶とほうじ茶の違いも判らんて非常識な。」
「番茶を飲んでるて、あれで褒めたつもりやろか。番茶やで、番茶。」
「XXXXさんてほんまに京都人?」
いささかエピソードが長くなりましたが、事程左様に京都人はほうじ茶に対するこだわりが強いのです。
それもそのはず、煎茶や緑茶、抹茶などとは比較にならないほど京都で消費量が多いのはほうじ茶なのです。
では、これから京都人が愛してやまないほうじ茶の魅力を解き明かしてみましょう。
お茶の種類 ほうじ茶・番茶・玄米茶
①ほうじ茶
煎茶、茎茶、番茶などをきつね色になるまで強火で炒って(ほうじて)、香ばしさを引き出したお茶のことです。
この他に、煎茶や番茶の仕上げ加工工程で選別した形の大きい葉や茎を混ぜ合わせて炒った(ほうじた)ものも含まれます。
ほうじ機でほうじ香が出るまで約200℃で加熱し、直ちに冷却します。
炒る(ほうじる)ことによって、カフェインが昇華したすっきりとした軽い飲み口が特徴で、食事中にも就寝前にもガブガブと気軽に飲めるお茶です。

ほうじ茶の茶葉

ほうじている写真

湯吞とほうじ茶の茶葉と急須
②番茶
番茶は「番外茶」からきているといわれており、大きく4種類に分類されます。
茶葉の摘採期や品質、地域によってさまざまな意味の番茶があります。
1.一番茶の手摘み、あるいは若芽を摘採した後の遅れ芽を摘採したもので、品質は良好。(専門的には「一茶番」と呼ばれる。)
2.三番茶を摘み取らず、そのまま放置しておいて枝葉が伸びた秋に摘採したもので、量としては圧倒的に多い。(専門的には「秋冬番茶」と呼ばれる)
3.仕上げ加工工程で大きく扁平な葉を切断せずに取り出して製品化したもの。(専門的には「頭」と呼ばれる。)
4.地元消費を目的に特殊製法で造られたもの。(例として「京番茶」や「阿波番茶」など。)
いずれにしても、摘採期、品質、地域などで日本茶の主流から外れた番外のお茶を指しています。
一説には遅く摘み取ったお茶、つまり「晩茶」から転じて「番茶」となったとも、番小屋で待機している最中に兵士が飲んだ安いお茶から「番茶」と呼ばれるようになったともいわれています。
③玄米茶
水に浸して蒸した米を炒り、これに煎茶や番茶を同等の比率で加えて造られたお茶のことです。
炒り米の香ばしさと、煎茶と番茶のすっきりとした味わいが楽しめます。
米が混じっていることで、煎茶と番茶の使用量が少なくなっていることからカフェインが少なく、子供やお年寄りにも安心して薦められるお茶でもあります。
ほうじ茶の魅力とは?
宇治茶を専門に扱うお茶の老舗「山本園茶舗」のご主人は、京都人とほうじ茶の関係についてこう語っています。
「京都の人が圧倒的に好むのはほうじ茶ですわ。世間一般の概念では、ほうじ茶いうたら煎茶とか緑茶に比べたら何となく格が下みたいに思われてますけどな。せやけど、ほうじ茶の茶葉の中には、ものすごい高級な品種のお茶の茎を集めて作ったもんもあるんですわ。例えば、玉露とか煎茶の茎の部分ばっかりを集めて造ったお茶のことを、京都ではかりがねといいますやろ。実は茎茶には、葉では出せへん甘みやまろやかさがあるんですわ。そのかりがねを炒って造ったかりがねほうじ茶を、京都の人はよう買うてくれはります。」
「うちの店でも、ほうじてたらその香りでお得意さんが駆けつけてくれはるんですけど、一番早う売り切れるんが茎ほうじですな。つまり、かりがねのほうじ茶ですわ。―――茎ほうじの元のお茶はれっきとした玉露とか煎茶ですし、茎茶独特の甘みやまろやかさもある。そのうえ、ほうじてあるさかい、香ばしい香りと優しい口当たりが際立っている。カフェインも飛んでしもてるさかい、子供とかお年寄りでも安心して飲める。ガブガブ飲めてしかも高級な茶葉を使うてる。おまけにほうじ茶は安い。―――こういう茎ほうじのよさをほんまにわかってるから京都の人はほうじ茶が好きなんですわ。」
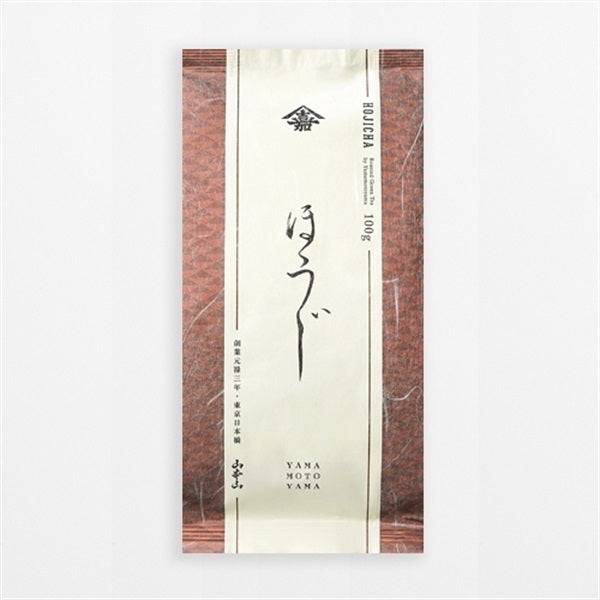
かりがねほうじ茶のパッケージ写真
このことからもわかるように、コラム子の知り合いの奥さんは生粋の京都人だったわけですね。
つまり、ほうじ茶を飲んでいる我が家を番茶を飲む輩と一緒にせんといてほしい、ということです。
ほうじ茶と番茶、ここが違う!
ほうじ茶と番茶。
どちらも日常的に親しまれているお茶ですが、お茶にうるさい京都人が断然支持するのはほうじ茶であることは先に述べたとおりです。
実際、ほうじ茶と番茶では製法、味わい、香りなどが全く異なるのです。

ほうじ茶を入れている写真
違い ① 原料と製法
冒頭で紹介したとおり、ほうじ茶とは茶葉を高温で焙煎することで造られるお茶です。200℃前後の高温で5~10分ほど過熱して造られます。茶葉には煎茶や番茶、茎茶などが用いられます。この焙煎によって茶葉は褐色になり、独特の香ばしさが生まれます。
これに対して、番茶は一番茶、二番茶の後に新たに伸びてきた三番茶や、秋ごろに摘まれる茶葉を揉み、蒸し、乾燥させて造られます。番茶には焙煎の工程はありません。
違い ② 香り
ほうじ茶の最大の魅力は何といっても香ばしい香りです。香りのもととなる成分は「ピラジン」と呼ばれ、茶葉に含まれるアミノ酸と糖が過熱されることで生成される香気成分です。「ピラジン」にはリラックス効果があることが最近の研究によってわかってきました。さらに、血管を広げて血行を促進させる効果もあり、冷え性改善にもつながると注目が集まっています。
番茶は焙煎していないため、ほうじ茶のような強い香りはありませんが、茶葉本来の穏やかで優しい香りは楽しめます。
違い ③ 味わい
ほうじ茶は香ばしさに加えてまろやかな甘みとコクが感じられます。これも焙煎の影響です。
もともと茶葉に含まれているカテキンなどの渋み成分は、高温加熱によって水に溶けない成分に変化します。
更に、焙煎によって茶葉に含まれる糖分がカラメル化し、より一層甘みが増すのです。
これに対して、番茶はカフェインやタンニンが少ないことから渋みが少なくすっきりした味わいが特徴的です。
また、入れてから長時間が経っても苦みが出にくいので保存に適しています。
そして、誰でも簡単に入れることができる便利なお茶でもあります。
いかがでしたか。このようにほうじ茶と番茶では製法、香り、味わいに違いがあります。
それぞれに特徴がありますから、シーンや用途に応じて適当なお茶を選んでみてください。
例えば、リラックスしたいときや就寝前にはほうじ茶を。
食事中や気分転換したいときにはピラジンの豊富なほうじ茶を、という風に。
人気のほうじ茶アレンジレシピ紹介
どんな食べ物にもよく合う上に、脳のリラックス効果や冷え性の改善にも一役買うなど、健康志向の現代社会で最近俄然注目を浴びるようになってきたほうじ茶ですが、もともとほうじ茶人気の高かった京都では、ここ数年の間にほうじ茶専門店が続々オープンしています。
そういうお店では、ほうじ茶ケーキやほうじ茶パフェ、さらにはほうじ茶ラテなどの様々なほうじ茶のアレンジレシピが開発され、提供されています。

ほうじ茶パフェ

ほうじ茶のシフォンケーキ

ほうじ茶ラテ
もはや、ほうじ茶の魅力は和菓子や和食に合うだけではなくなってきました、というところでしょうか。
ほうじ茶専門店として有名なお店は以下の通りです。
① HOHO HOJICHA 焙茶専門店 京都駅店(下京区)
② UJI MATCHA GOENCHA 京都ぎょくろのごえん茶蛸薬師店(中京区)
③ 一保堂茶舗 京都本店(中京区)
④ 福寿園 京都本店(下京区)
⑤ 山本園茶舗(北区)
この記事を書いた人
つばくろ(Tsubakuro)
京都生まれ、京都育ち、生粋の京都人です。
若い頃は京都よりも賑やかな東京や大阪に憧れを抱いていましたが、年を重ねるに従って少しづつ京都の良さが分かってきました。
このサイトでは、一見さんでは見落してしまう京都の食を巡る穴場スポットを紹介します。