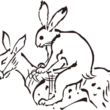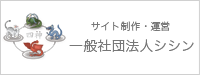広告
adsense4

はじめに
はんなりして耳に心地よい「おもたせ」という京ことば。
最近、目にする機会が増えてきました。
例えば、雑誌のスイーツ特集記事で、あるいはお店のカタログで、皆さんも一度は見かけたことがあるのではないでしょうか。
つい先日、コラム子も、リーガロイヤルホテル京都が今年のクリスマスケーキを「えらべる『おもたせChristmas』」と銘打って販売していることを知りました。
リーガロイヤルホテル京都だけではありません。
雑誌記事でも店舗のカタログでも、「ちょっとしたおもたせや、手土産にどうぞ」という風に「おもたせ」と「手土産」を混同して使っている例を実にたくさん見かけます。
中には、「『おもたせ』用の手土産を購入」だの、「ⅩⅩⅩへ行って『おもたせ』のお菓子を買ってきた」だのという使い方をしているケースもあります。
どうやら、自分が持っていく手土産のことを「おもたせ」と表現している場合が多々あるようです。
つまり、手土産を小粋で上品に言い表すことばとして、「おもたせ」を用いているわけですね。
しかしながら、生粋の京都人は決してこんな使い方はしません。
「おもたせ」と手土産は実は全く違うからです。
今回は誤用されがちな京ことばの代表格、「おもたせ」の本来の意味を解説していきます。
「おもたせ」ということばが京都で使われるのはこんな時

京都のとあるお宅でホームパーティーが開かれることになりました。
パーティーでなければ、茶話会でも構いません。
そこに集う人たちは、それぞれ趣向を凝らした手土産を持ち寄っています。
もちろん、会場を提供しているお宅の主人もご馳走を用意しています。
しかし、ときに珍しい食べ物や洒落た手土産をもらうと「せっかくやから、みんなでご馳走になろう。」ということになります。
そういう時、家の主人はこういいます。
「おもたせですけど、上等のお菓子ですさかいみなでよばれまひょか。」
そういって主人は頂き物のお菓子を全員に披露します。
こういう時に使うのが「おもたせ」です。
つまり、手土産に頂戴したものを、その場に集うみんなで一緒に食べる時に使われる京ことばが「おもたせ」なのです。
「おもたせ」とは単なる手土産を指すことばではなく、こういう限られた場面でしか使われないことばであるといえます。
主人が用意したものではなく、お客が持ってきてくれたものを参加者全員で味わうときに使われる京ことば。―――それが「おもたせ」です。
京都に縁の薄い東京の雑誌編集者が、気の利いた手土産を「おもたせ」だと誤用するのはまだしも、れっきとした京都の料亭やホテルが自らのホームページで「おもたせカタログ」などと自社の手土産を紹介しているのは、実に嘆かわしいことです。
手土産とおもたせの用途別選び方の手引き
①手土産の場合
手土産とは、訪問先に敬意や感謝を表すときに使われることが多いですね。とりわけ、ビジネスシーンで取引先の上司などに誠意を示すために、訪問者が持参するのが典型的な手土産の使われ方ではないでしょうか。
フォーマルな状況で利用されることがほとんどですから、あくまでも「目上の人に対する尊敬の念」をはらった品物を選ぶのが適当でしょう。ビジネスシーンでの手土産の選び方としては、相手企業の業種や地元の特産品などに心配りした品物を選ぶのがおすすめです。
例えば、地元の神戸牛を使ったビーフカレーなど。
また個人的な用途で手土産を持参する際には、相手の家族構成や生活習慣に心配りした品物が喜ばれます。
例えば、子供のいる家庭ならおやつとか、食卓での家族の会話が弾むような高級感あふれるパンとチーズなど。
②「おもたせ」の場合
先に述べたように、「おもたせ」とはあくまでも訪問先で主人とお客の両方が一緒に食べることを前提としています。

そのため、ホームパーティーや茶話会、バーベキューやピクニック、お花見などといったカジュアルな場面にふさわしい品物を選ぶのがよいでしょう。
例えば、茶話会や懇親会などでは、配りやすいクッキーやチョコレート、それから和菓子など。

クッキーの詰め合わせ

チョコレートの詰め合わせ

桜餅
また、季節を代表する旬のフルーツを用いたお菓子なども歓迎されます。

シャインマスカットのタルト

ホームパーティー
ホームパーティーやピクニックなどの場面では、みんなでワイワイ騒いで分け合えるピザや寿司などのパーティセットがその場の雰囲気を盛り上げるでしょう。

ピザ
ここで特筆すべきは、こういう場合京都では鯖寿司がことのほか「おもたせ」として重宝されることです。

鯖寿司
「おもたせ」と「鯖寿司」の関係
京都人と鯖寿司には切っても切れない関係があります。
今さらいうまでもないことですが、海のない京都では昔から魚を食べる機会に恵まれませんでした。
しかし、唯一の例外がありました。
それは、若狭で漁れる鯖です。
若狭で大量に獲れる鯖に塩を振って、通称「鯖街道」というルートをたどって、2~3日がかりで京の都に運ばれるようになったのは戦国時代からです。

鯖街道のたたずまい

出町に今も残る鯖街道の終点を表す石碑
冷蔵保存の技術が未熟だった当時、腐るのを防ぐため、鯖に大量の塩を振るのはやむを得ないことでした。
ところが偶然とはよくしたもので、塩をした鯖を「鯖街道」を通って運ぶと、京都に到着する頃にはちょうどいい塩加減になることに人々は気づきます。
それを利用して、江戸時代に「鯖寿司」が京都で誕生したというわけです。

鯖寿司
冷蔵保存の技術が発達した現代でも、京都では非常に塩鯖が好まれます。そして、「鯖寿司」は昔同様、今でも「ハレの日」のご馳走として京都人に熱烈に愛されているのです。
京都三大祭りである「祇園祭」、「葵祭」、「時代祭」に鯖寿司を作ってお祝いするのは京都人なら当たり前の風習です。
こうしたことからもわかるように、みんなに喜んでもらいたい、しかも貴重な品物を送りたいという時の「おもたせ」に打ってつけの手土産といえば、京都では一も二もなく「鯖寿司」が選ばれるのです。
参考文献
①「おひとりからのしずかな京都」柏井壽 著 SB新書 2022年発行
②「手みやげを買いに」 京阪神エルマガジン編集 京阪神エルマガジン社 2022年発行
③「京町家・杉本家の京の普段づかい」 杉本節子 著 PHP新書 2016年発行
この記事を書いた人
つばくろ(Tsubakuro)
京都生まれ、京都育ち、生粋の京都人です。
若い頃は京都よりも賑やかな東京や大阪に憧れを抱いていましたが、年を重ねるに従って少しづつ京都の良さが分かってきました。
このサイトでは、一見さんでは見落してしまう京都の食を巡る穴場スポットを紹介します。