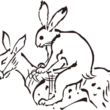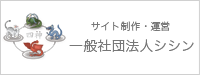広告
adsense4
はじめに
海外からの観光客が押すな押すなと詰めかけている京都の街。
市街を歩いても、市バスに乗っても、地下鉄に乗っても、どこにでも見かける外国人。
そんな光景が日常化して久しいですが、海外の観光客が宿泊する施設を巡って、京の伝統的な食文化に大きな異変が生じているらしいことがわかってきました。
コラム子がそれに気づいたのは今から約半年前のこと。
いつもと変わらぬ家の近所を歩いていた時のことでした。
コラム子が暮らす四条大宮周辺は、ここ10年ほどの間にビジネスホテルや民泊が激増してきた地域です。
市の中心部であり、どこへ行くにも交通アクセスが良く、それでいて静かな住宅街としての顔も持ち合わせている―――そんな理由で外国人旅行者目当ての小さなビジネスホテルや民泊が密集したのでしょう。
さて、去る春の朝、表通りの四条通りから一筋右に入った路地の中を歩いていた時、コラム子はとある民泊の前に料理を食べた後の空の食器が雑然と積み上げられた船を見かけたのです。
ポイ捨てにされるようなコンビニやスーパーで買ったと思しきプラスチックの空の弁当箱の残骸なんかではありませんでした。
由緒ある清水焼か京焼か、とにかく一目見るだけで高価だとわかる食器の数々が空のまま無造作に散らばって、船に積まれているのです。
そして、船の後ろには「井傳(いでん)」の文字が。
この文字を見て、コラム子は京の食文化を代表する仕出しの仕事が様変わりしたらしいことに気づきました。
「井傳」といえば錦市場のお膝元にあって、中京区でも筆頭に挙げられる仕出しの老舗です。

「井傳」の表玄関

「井傳」の前に停められたワゴン
中京や下京の町衆を相手に、ハレの日に、ケの日に、あるいは大店のもう一つの台所として各家々の味の好みを熟知して、お客の信頼を勝ち取りながら料理を届けてきた本物の仕出し屋です。
その「井傳」がなぜ民泊に料理を配達することになったのか?
その時、コラム子は不思議に思いながらもよくわかりませんでした。
ところが、日を経ずして似たような光景にまたしても遭遇したのです。
今度もやはり表通りから一筋入った裏路地の別な民泊の前でした。
そして、その時の船に書かれていた仕出し屋の名前は「辻留」。
これまた東山三条の茶懐石を専門に配達する、京都屈指の仕出し屋です。
更に更に、3度目は下京の室町筋の有名な仕出し屋「木の婦」の船までも。
これはどう考えても、ただの偶然ではなさそうです。
今どきの京の仕出し文化は一体どうなっているのか?
それについて調べましたので、これから解説していきます。
仕出しの仕事とは?
京都独特の食文化の担い手である仕出し屋。
出前でもない、デリバリーでもない、ケータリングサービスでもない、その特徴は一体どこにあるのでしょうか?
それは、「お客のどんな要望にもこたえる料理を届ける」をモットーにしていること、といえるでしょう。
例えば、京の仕出し屋は酒のおつまみなどのたった1品でも料理して届けてくれます。
事実、先に挙げた「井傳」が、室町筋の大店であった「杉本家」に酒の肴の1品を配達した記録なども残っています。
そして、仕出し屋のもう1つの特色は料理を見事な器に美しく盛りつけた状態で届けてくれることでもあります。
更にそのうえ、食べ終わったお客は空の食器を片づけたりする手間もいらず、そのまま器を船に置いたまま玄関に出しておけばよいのです。―――後片付けは、仕出し屋が食器を回収しに来てやってくれるからです。
料理をしてくれる、上等な器に盛りつけてくれる、面倒な後片付けも考えなくてよい。―――いたれりつくせり、のサービスを提供してくれる料理屋。
それが、京の仕出し屋です。

仕出し料理
町衆に育てられた仕出し文化
昔は町内に必ず2~3軒は仕出し屋があったといわれるほど、仕出しは町衆とともに育った文化だといえます。
室町筋や西陣の大店に毎朝天秤棒を担いで御用聞きに回り、店の旦那から「今日のええとこ、何品か持ってきて。」といわれると、夕方には料理した品物を届ける。―――そんな光景が日常的に見受けられました。
まさに、仕出し屋はご近所のもう1つの台所でもあったのです。
例えば、コラム子が子供の頃京都には衛生掃除という習慣がありました。
梅雨の明けた夏の日に、町内で一斉に徹底的な大掃除をやるのです。
両隣りの人たちと助け合って、各家の畳をはがして埃をたたいたり、天井を拭いたりと日ごろ行き届かない掃除をするのですが、その日の夕方はどこも決まって仕出し屋に料理を注文しました。
そして届けてもらう料理の内容も、別にお客様に出すようなごちそうでもなんでもなく、せいぜいでこんまき(昆布巻き)や汁物、ご飯、あと2品くらいのごくありきたりのおかずでした。
仕出しをとる。―――改まって肩ひじ張った気負いはなかったと思います。
大店の旦那衆にとどまらず、一般庶民にとっても仕出しをとることは身近な行為でした。
時には、仕出し屋はお客の家に食材と調理器具の一切を持ち込んで。目の前で料理することもありました。
仕出し屋もコツを心得ていて、お客によって味付けを変えたりするなどの心配りも怠りません。
加えて、仕出し料理は調理されてから時間の経過した冷たい状態で供されるため、冷めてもおいしく食べてもらうなどの綿密な計算が必要とされます。
また、大店の旦那衆は舌が肥えていて細かい味の注文を出します。
しかし、そうした訓練のおかげで料理人の腕も鍛えられるわけです。
室町や西陣の旦那衆はそういう仕出し屋を信頼して、着物や帯の新作発表の会にお得意様を招待するときなど、安心して仕出し料理をとってもてなすことができるのです。
このようにして、客と料理人の密接な関係のもとで京都の伝統的な仕出し文化は発展してきました。
ハレの日にパッとお金を使う京都人の気質と仕出しによるおもてなし
仕出し文化が京都に深く根付いた背景には、京都人特有のお金の使い方が大きく影響していることも見逃せません。
普段は地味で質素な暮らしをする京都人ですが、一方でお祝いごとや来客などの「ハレの日」には思い切った贅沢をしようという、京都人ならではの見栄っ張り根性があって、それが仕出し文化を発展させていきました。

節句やお食い初めなどの佳節にパッとお金をはたいて仕出しをとる。
例えば、コラム子のご近所さんの場合など、高価な仏壇を購入したから知り合いに是非とも見てもらいたいという理由で、近所のだれかれを招待して高級な仕出し料理でもてなされました。
コラム子の家は家族全員招待されてご相伴に預かったのですが、まさにあれなどは京都人の見栄っ張り気質が現れた典型的な例だったと思います。
そもそも、京都では人が来た時には手作り料理を出さないという不文律があります。
どんなに料理上手でも、家庭料理にはその家その家特有の味があるからです。
お客の口に合わない場合も自ずと出てきます。
口に合わない料理を食べさせたりしたら申し訳ない。
その点プロの料理人に任せておけば、間違いなく万人受けする味付けをしてくれますから、安心してお客に出せるのです。
京都ではお客に出す場合は、コーヒー1杯でも喫茶店から届けてもらうのが正式なもてなし方です。
大切なお客様には熟練のプロの味を堪能してもらうこと。―――これが京都のおもてなしの精神です。
何事もプロの技(=自分にできる最高のこと)でもてなすのが礼儀である。こうした価値観に基づいてお客に接するのが京都人気質です。
特に洛中人にはその傾向が強いといえるでしょう。
また、ハレの日と同様ケの日にも仕出し料理は重宝されてきました。
法事などで、居並ぶ親族が一堂に会して仕出しのお膳につく光景は京都ではごくありきたりのものですね。

法事の席でお膳を囲む人々
慶弔を問わず、仕出し料理は使い勝手が良かったのです。
そういう仕出し文化がなぜ様変わりしつつあるのか?
創業200年を超える仕出しの老舗「菱岩」の5代目ご主人のインタビュー記事を読む機会がありました。
そこには「最近、仕出しの需要は激減しています。」とありました。
続けて、「仕出し料理や仕出し弁当を『文化』としてビジネスホテルや民泊に提供することは、ハレの日や日々の暮らしを彩る京都の伝統的な文化を観光客に体験してもらう機会につながっています。宿泊施設と提携しながら、宿泊客のニーズに応じる宿泊客向けのメニューを開発したり、伝統的な京料理に外国人向けのユニークな一工夫も加えるなど、試行錯誤を重ねています。」とも書かれていました。
同時に、民泊やビジネスホテルの客室にまで直接届けるようにしていることも、外国の宿泊客には高級感あふれる器に盛りつけた料理の提供は喜ばれること、使い捨てではない仕出しならではの回収システムが環境への意識の高い宿泊客に評価されることなども述べられています。
とはいえ、これを一読してコラム子が即座に抱いた感想は以下のようなものでした。
宿泊客のニーズに応えるといったところで、所詮一回限りの一見さんに過ぎないではないか。
伝統的な仕出しの文化を育ててきた根っこにあった、味にうるさいお客(旦那衆)の要望に応えるべく料理の研鑽を重ねて相互の信頼を築くというスタイルと民泊やビジネスホテルの一見さんの宿泊客を相手にするのは、全く反対ではないか?
なんといい訳したところで、京都の仕出し屋は今や存亡の危機に立たされているというのが実情だろう。
そうでなければ京都を代表する仕出しの老舗が、次から次へと四条大宮くんだりの民泊やビジネスホテルまでわざわざ配達をするわけがない。
民泊の経営者と提携しながら宿泊客のニーズをつかむという建前だが、実際は民泊のオーナーは中国人であることがほとんど。
彼らは人の住まなくなった民家を買い上げて改装を建築業者に任せると、後はサッサと中国へ帰国してしまう。
民泊の経営者自身が日本にいない。
こういう、いわばほったらかしで宿泊客をどんどん泊め続けている施設と提携していくことが本来の仕出し文化にとって果たして良いことなのだろうか?
慶弔を重んじて仕出しをとる慣わしが廃れていく現在で、仕出し文化が生き延びるにはこの方法しかもはや残されていないのだろうか?
いささか長くなりましたが、以上が民泊やビジネスホテルのひしめく地域で、仕出し文化の激変を目の当たりにしたコラム子の率直な感想です。
参考文献
①「西陣がわかれば日本がわかる」 吉川哲史著 1990年 朝日新書
②「京のくらしに息づくおもてなしの心『仕出し』」 2021年 京都観光 Navi プラス
③「京のおもてなし料理:町衆と寺院が育てた仕出し文化」京都新聞社編 1999年 京都新聞社
この記事を書いた人
つばくろ(Tsubakuro)
京都生まれ、京都育ち、生粋の京都人です。
若い頃は京都よりも賑やかな東京や大阪に憧れを抱いていましたが、年を重ねるに従って少しづつ京都の良さが分かってきました。
このサイトでは、一見さんでは見落してしまう京都の食を巡る穴場スポットを紹介します。